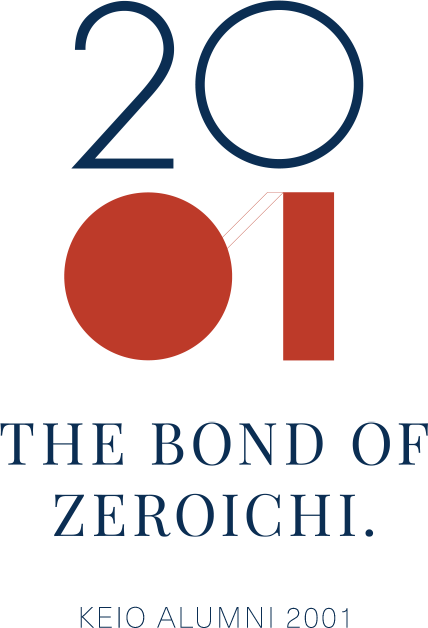
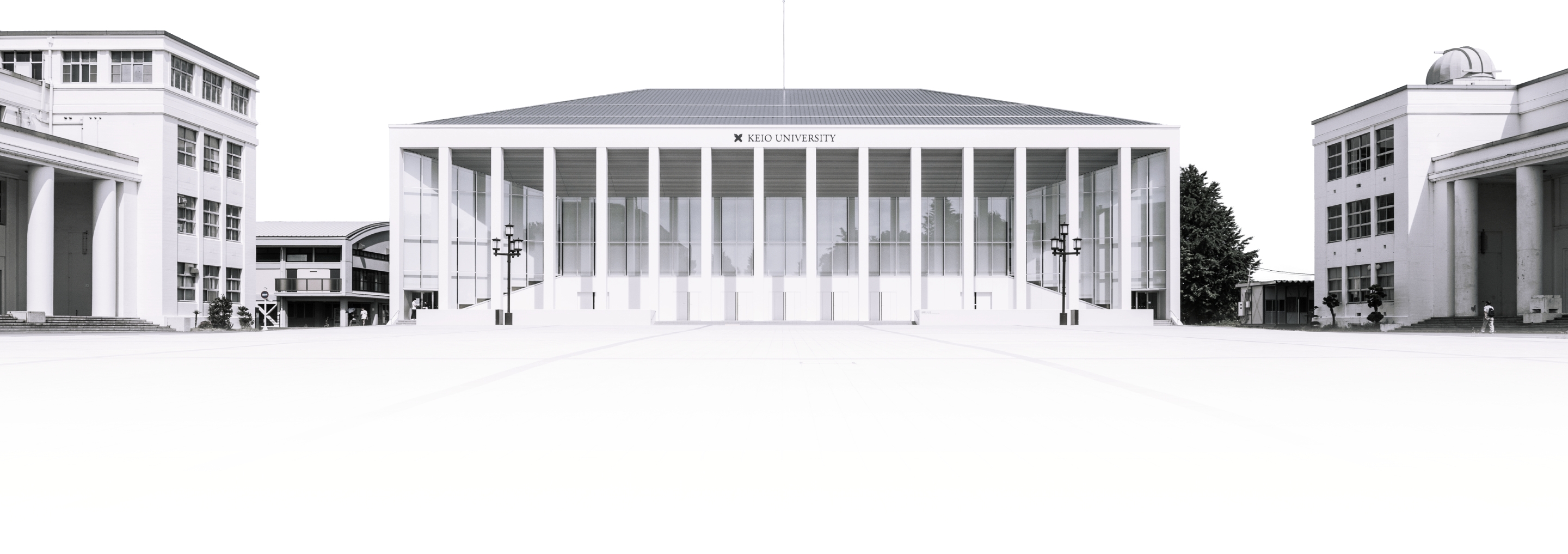
ゼロイチのみなさまへ大切なお知らせ
【ゼロイチ同期紹介企画Vol.3】京都を拠点に自然の造形美を伝え続ける吉村紘一さん
卒業25周年を迎えるにあたり、ゼロイチ同期の活躍を紹介するブログ企画を立ち上げました。社会との絆、仲間との絆、次世代への絆…さまざまな絆をつなぎ、前向きな活動をされている同期の仲間をご紹介します。第3回目は京都を拠点に「自然の造形美を伝える」活動を続ける吉村紘一さんです。

【質問内容】
Q 出身学部・学科、ご所属ゼミ・サークルなどを教えてください。
総合政策学部に入学して途中で環境情報学部へ転部して卒業しました。
ゼミは金子満先生の研究室で、サークルはアイスホッケーサークル「ELK」とAIESECに所属していました。
Q 現在のお仕事や活動について教えてください。
京都を拠点に株式会社ウサギノネドコという法人を経営しています。「自然の造形美を伝える」を事業コンセプトにしていまして、アートやデザインのように鉱物・植物・動物などの自然の造形美を生活の中で楽しむことを提案しています。
京都では昭和初期に、宮大工であった私の曽祖父が建てた京町家を改築して、ミセ、ヤド、カフェという複数の業種が入った店舗を運営しています。
Q 現在のお仕事・活動に携わることになったきっかけは?
子どもの頃から手を動かしてものを作る、図工や美術の授業が好きでした。慶應義塾高校では選択美術の授業があって鍛金(たんきん)や木工が楽しかったのをよく覚えています。
それから後述するSFCでのさまざまな出会いや経験を経て、2001年から2011年までの10年間はアサツーディ・ケイ(現:ADKグループ)という広告会社でマーケティング戦略の立案や、広告制作に関わっていました。
仕事には非常にやりがいを感じていましたが、一方で「自分自身の手で生み出したものづくりをしたい」という思いが強くなり、入社6年目の2006年に「美しい植物のかたち」をコンセプトにした「Sola cube(ソラキューブ)」というプロダクト(写真下)を作りました。

それが大きなきっかけとなり、植物だけでなく、植物・鉱物・動物などの「自然の造形美」全体を包括できる事業を始めようと思い至り、2012年に京都でウサギノネドコを開業しました。
Q 学生時代に特に印象に残っている出来事やエピソードはありますか?
印象的だったことはいくつかあります。大学一年生の時の一般教養で「現代芸術」という授業を選択したのですが、美術館で館長をされている方が授業を受け持たれていました。自分はアートの世界への興味関心が強かったので「(SFCを)やめて(美術系の大学を)受験し直そうと思っているんですけど…」と相談したら「いや、もったいないよ」とアドバイスをいただきました。そして、「SFCではコンピュータアートや、コンピュータグラフィックスなど、最先端のアートの勉強ができるじゃない」と言ってくださったんですよ。
それがきっかけになり、日本で最初のCGのスタジオを作られた金子満教授のゼミに所属し、3DCGのアニメーションを企画・製作していました。そんな中、自分自身が作った映像が当時のテレビ番組「たけしの誰でもピカソ(テレビ東京)」で放送されたことがあって、本当にワクワクしました。
自分が生み出したものをメディアを通じて世の中に伝えられるというのは今の活動にも繋がる原体験だったと言えます。
また、この活動が直接的な影響にもなり、メディア業界、広告業界への就職活動を行い、結果的に1社目では広告会社に勤めることになりました。
Q 同期とのつながりが、あなたにどんな影響を与えていますか?今でも連絡を取り合う同期の方はいますか?
経済学部卒の柳井裕至さんとは慶應義塾高校時代から同じクラスで、大学時代には二人で1ヶ月半ヨーロッパをバックパックで旅行しました。イタリア南部のロコロトンドという村でのボランティア活動から始まり、スペイン、ドイツ、フランス、スイスと5カ国を電車で旅しました。その体験は今もとても良い思い出です。
今は高い頻度で連絡を取り合う間柄ではありませんが、私自身は彼の真摯に向き合う姿勢や、本質を探究・追求しようという姿勢に刺激を受け、今でも影響を受けていると思います。
Q 社会に出て慶應義塾大学のつながりを感じたり、慶應出身で良かったと感じたりすることはありますか?それはどのようなときですか?
久々に慶應の同窓会などに行くと、経済界で活躍している同志、中でも経営者が多いなと感じます。上場を果たした企業の経営者や、ゼロから起業してチャレンジをしている人もいて多方面に大いに刺激を受けています。
Q 卒後25年を振り返って、どのようなことを感じますか?
慶應義塾高校の3年間と、その後は藤沢キャンパスで4年間を過ごしました。在学中はその恵まれた環境に全く気づくことができませんでしたが、卒業から時が経つにつれて、仲間・友人、教員陣、そして校舎を含めた学校の環境など、全てが素晴らしかったなぁと今では当時の自分が置かれていた環境に深く感謝しています。
集団で行動することが苦手で、天邪鬼だったこともあり、在校時は「若き血」を歌った数もおそらく数えるほどしかありません(笑)。愛校精神に欠けていたと思います。大きな学校行事にもほとんど顔を出しませんでしたが、こうしてまたインタビューを通して慶應義塾と関われることに喜びを感じます。
Q 同期や後輩に向けて伝えたいメッセージはありますか?
私自身にとって大学時代は「実験の期間」で、学外・学内問わず、やりたいことを全部チャレンジする期間でした。大いにチャレンジをしましたが、一方で盛大な失敗も数知れません。後輩の皆さんにも是非、たくさんのことにチャレンジして欲しいですし、同時にたくさんの失敗を重ねてもらえたらと思います。歳を重ねるごとに「思い切って失敗する」ということができづらくなってきますし、若い時ほど失敗して失うものは何もないので。
Q 50歳を目前にした今、これからどんな挑戦をしたいですか?
あと2週間後(本日は2025年7月15日)に渡米して、ニューヨークのSHOPPE OBJECTという全米から小売店のバイヤーが集まる展示会に出展します。Sola cubeという2006年に生み出したプロダクトが今もメインの商材で、それをプレゼンテーションして販路拡大をする予定です。海外での販路はこれまでもそれなりに拡大をしてきましたが、まだ伸び代があるはずなので、更なるチャレンジをしていきたいと思っています。
あとは人生を通して「美を追求する」ことをテーマにしていきたいので、美術の世界でどんなチャレンジができるのか?ということや、「ウサギノネドコ」や「Sola cube」など、これまで作り上げてきたブランドをどこまで育てられるか?は、これからも挑戦したいところです。
私の先祖は京都で代々、宮大工を営んできたのですが、曽祖父に当たる吉村富三郎が昭和14年に自身の弟子のために建築した町家が空き家で、そこを店舗にしようと計画し、動き始めたのがウサギノネドコのきっかけです。
そのような経緯もあって先祖に思いを馳せることが多く、「(自分自身も)100年後に残るものをつくりたい」と考えています。よほどの強度がないと100年は残らないはずですが、自分が死んだ後にも残るものづくりに挑戦したいと思います。
Q 次の25年で社会や周囲にどう貢献していきたいですか?
この数年は自分のやってきたことが、誰か他者の役に立たないかなという思いが芽生えています。自分の事業をしながら、自分の考えや行なってきたことを体系化して、教育の現場や、講演などの機会で人に伝え、それが誰かの役に立てれば嬉しいです。

【質問内容】
Q 出身学部・学科、ご所属ゼミ・サークルなどを教えてください。
総合政策学部に入学して途中で環境情報学部へ転部して卒業しました。
ゼミは金子満先生の研究室で、サークルはアイスホッケーサークル「ELK」とAIESECに所属していました。
Q 現在のお仕事や活動について教えてください。
京都を拠点に株式会社ウサギノネドコという法人を経営しています。「自然の造形美を伝える」を事業コンセプトにしていまして、アートやデザインのように鉱物・植物・動物などの自然の造形美を生活の中で楽しむことを提案しています。
京都では昭和初期に、宮大工であった私の曽祖父が建てた京町家を改築して、ミセ、ヤド、カフェという複数の業種が入った店舗を運営しています。
Q 現在のお仕事・活動に携わることになったきっかけは?
子どもの頃から手を動かしてものを作る、図工や美術の授業が好きでした。慶應義塾高校では選択美術の授業があって鍛金(たんきん)や木工が楽しかったのをよく覚えています。
それから後述するSFCでのさまざまな出会いや経験を経て、2001年から2011年までの10年間はアサツーディ・ケイ(現:ADKグループ)という広告会社でマーケティング戦略の立案や、広告制作に関わっていました。
仕事には非常にやりがいを感じていましたが、一方で「自分自身の手で生み出したものづくりをしたい」という思いが強くなり、入社6年目の2006年に「美しい植物のかたち」をコンセプトにした「Sola cube(ソラキューブ)」というプロダクト(写真下)を作りました。

それが大きなきっかけとなり、植物だけでなく、植物・鉱物・動物などの「自然の造形美」全体を包括できる事業を始めようと思い至り、2012年に京都でウサギノネドコを開業しました。
Q 学生時代に特に印象に残っている出来事やエピソードはありますか?
印象的だったことはいくつかあります。大学一年生の時の一般教養で「現代芸術」という授業を選択したのですが、美術館で館長をされている方が授業を受け持たれていました。自分はアートの世界への興味関心が強かったので「(SFCを)やめて(美術系の大学を)受験し直そうと思っているんですけど…」と相談したら「いや、もったいないよ」とアドバイスをいただきました。そして、「SFCではコンピュータアートや、コンピュータグラフィックスなど、最先端のアートの勉強ができるじゃない」と言ってくださったんですよ。
それがきっかけになり、日本で最初のCGのスタジオを作られた金子満教授のゼミに所属し、3DCGのアニメーションを企画・製作していました。そんな中、自分自身が作った映像が当時のテレビ番組「たけしの誰でもピカソ(テレビ東京)」で放送されたことがあって、本当にワクワクしました。
自分が生み出したものをメディアを通じて世の中に伝えられるというのは今の活動にも繋がる原体験だったと言えます。
また、この活動が直接的な影響にもなり、メディア業界、広告業界への就職活動を行い、結果的に1社目では広告会社に勤めることになりました。
Q 同期とのつながりが、あなたにどんな影響を与えていますか?今でも連絡を取り合う同期の方はいますか?
経済学部卒の柳井裕至さんとは慶應義塾高校時代から同じクラスで、大学時代には二人で1ヶ月半ヨーロッパをバックパックで旅行しました。イタリア南部のロコロトンドという村でのボランティア活動から始まり、スペイン、ドイツ、フランス、スイスと5カ国を電車で旅しました。その体験は今もとても良い思い出です。
今は高い頻度で連絡を取り合う間柄ではありませんが、私自身は彼の真摯に向き合う姿勢や、本質を探究・追求しようという姿勢に刺激を受け、今でも影響を受けていると思います。
Q 社会に出て慶應義塾大学のつながりを感じたり、慶應出身で良かったと感じたりすることはありますか?それはどのようなときですか?
久々に慶應の同窓会などに行くと、経済界で活躍している同志、中でも経営者が多いなと感じます。上場を果たした企業の経営者や、ゼロから起業してチャレンジをしている人もいて多方面に大いに刺激を受けています。
Q 卒後25年を振り返って、どのようなことを感じますか?
慶應義塾高校の3年間と、その後は藤沢キャンパスで4年間を過ごしました。在学中はその恵まれた環境に全く気づくことができませんでしたが、卒業から時が経つにつれて、仲間・友人、教員陣、そして校舎を含めた学校の環境など、全てが素晴らしかったなぁと今では当時の自分が置かれていた環境に深く感謝しています。
集団で行動することが苦手で、天邪鬼だったこともあり、在校時は「若き血」を歌った数もおそらく数えるほどしかありません(笑)。愛校精神に欠けていたと思います。大きな学校行事にもほとんど顔を出しませんでしたが、こうしてまたインタビューを通して慶應義塾と関われることに喜びを感じます。
Q 同期や後輩に向けて伝えたいメッセージはありますか?
私自身にとって大学時代は「実験の期間」で、学外・学内問わず、やりたいことを全部チャレンジする期間でした。大いにチャレンジをしましたが、一方で盛大な失敗も数知れません。後輩の皆さんにも是非、たくさんのことにチャレンジして欲しいですし、同時にたくさんの失敗を重ねてもらえたらと思います。歳を重ねるごとに「思い切って失敗する」ということができづらくなってきますし、若い時ほど失敗して失うものは何もないので。
Q 50歳を目前にした今、これからどんな挑戦をしたいですか?
あと2週間後(本日は2025年7月15日)に渡米して、ニューヨークのSHOPPE OBJECTという全米から小売店のバイヤーが集まる展示会に出展します。Sola cubeという2006年に生み出したプロダクトが今もメインの商材で、それをプレゼンテーションして販路拡大をする予定です。海外での販路はこれまでもそれなりに拡大をしてきましたが、まだ伸び代があるはずなので、更なるチャレンジをしていきたいと思っています。
あとは人生を通して「美を追求する」ことをテーマにしていきたいので、美術の世界でどんなチャレンジができるのか?ということや、「ウサギノネドコ」や「Sola cube」など、これまで作り上げてきたブランドをどこまで育てられるか?は、これからも挑戦したいところです。
私の先祖は京都で代々、宮大工を営んできたのですが、曽祖父に当たる吉村富三郎が昭和14年に自身の弟子のために建築した町家が空き家で、そこを店舗にしようと計画し、動き始めたのがウサギノネドコのきっかけです。
そのような経緯もあって先祖に思いを馳せることが多く、「(自分自身も)100年後に残るものをつくりたい」と考えています。よほどの強度がないと100年は残らないはずですが、自分が死んだ後にも残るものづくりに挑戦したいと思います。
Q 次の25年で社会や周囲にどう貢献していきたいですか?
この数年は自分のやってきたことが、誰か他者の役に立たないかなという思いが芽生えています。自分の事業をしながら、自分の考えや行なってきたことを体系化して、教育の現場や、講演などの機会で人に伝え、それが誰かの役に立てれば嬉しいです。

二〇〇一年三田会の
輪
を広げましょう。



